
2024年4月21日。東京渋谷の代々木公園は、前日からつづく祝祭に真夏のような熱気を帯びていました。「個性を出してはたらいていいんだと伝えられたんじゃないか」「全員が当事者なんだと肌で感じられた」。
LGBTQ+当事者およびその支援者(アライ)とともに、“性”と“生”の多様性を祝福し、つながる“場”を提供することを目的に、2012年より代々木公園を中心に開催されてきた「東京レインボープライド」。その2024年開催の2日目、パーソルグループのブースに立ったデザイナー達は、自らがデザインした旗を背に、グッズを手に、これまでに感じたことのない想いを抱きしめていました。彼ら彼女らはいかにしてこの日を迎えたのか?その道程を追いました。

(左上)林 園子さん 採用ソリューション事業部 制作統括部 アートディレクター/デザイナー、(右上)須田 俊一郎さん 採用ソリューション事業部 制作統括部 デザイナー、(左下)播本 未来さん 採用ソリューション事業部 制作統括部 デザイナー、(右下)新井 光治さん 採用ソリューション事業部 制作統括部 デザイナー
1冊のハンドブックから全てがはじまった
林:
2022年に『Do you know LGBTQ?』というハンドブックの制作を依頼されたのが、はじまりです。声をかけてくれたのは、社内有志のプロジェクトである「RainbowPERSOL」の立ち上げメンバーの一人でした。ほんの数年前ですが、それでもセクシュアルマイノリティへの理解は現在と比べるとまだ浅く、ハンドブックもあくまで社内向けのものでした。
※パーソルグループでは2019年よりDEI(Diversity, Equity & Inclusion)の取り組みを開始。「RainbowPERSOL」は社員有志の「アライ(Ally)」コミュニティ。「東京レインボープライド」には2020年より協賛・企画協力を開始。
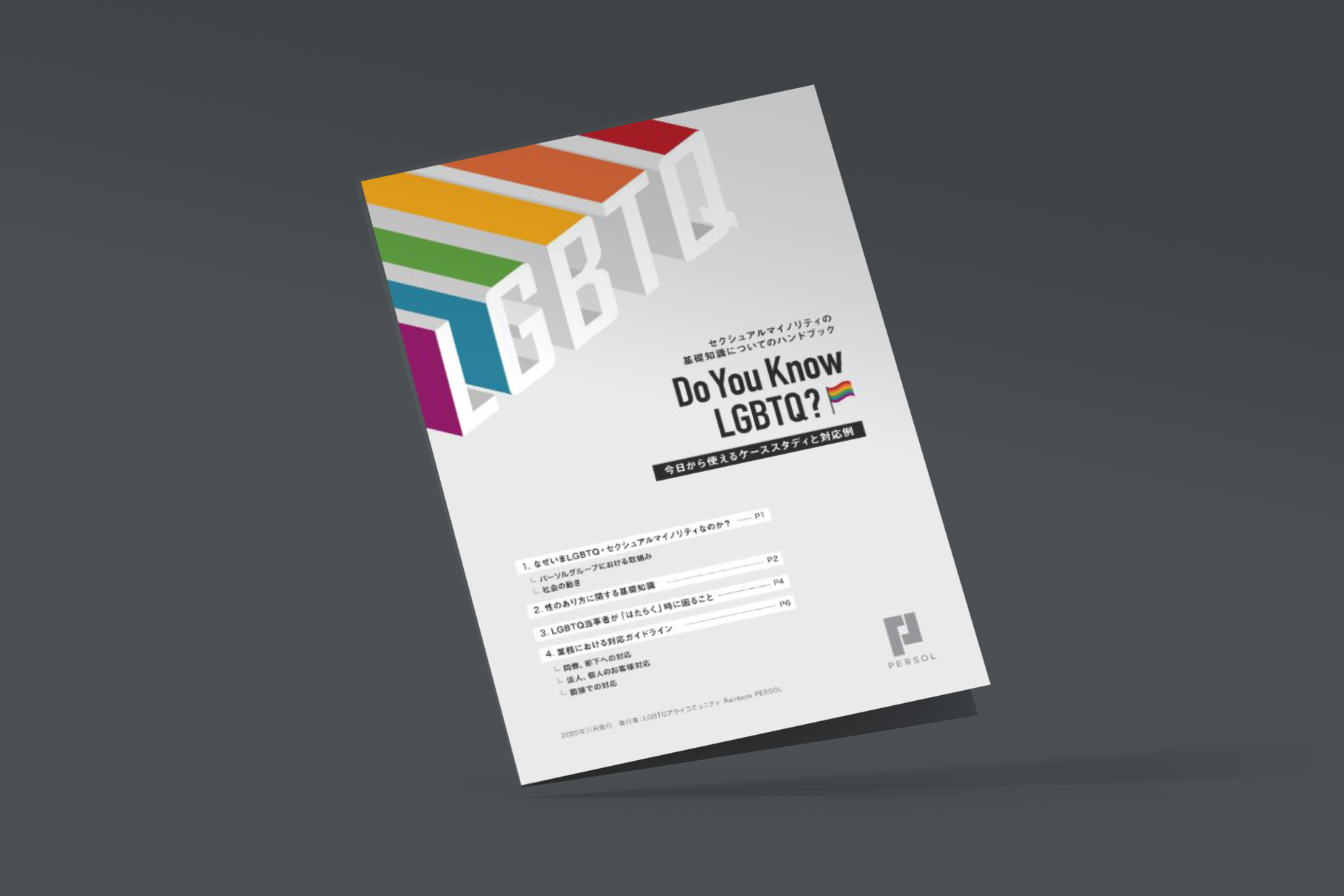
セクシュアルマイノリティの基礎知識についてのハンドブック『Do you know LGBTQ?』。性のあり方に関する基礎知識に加え、業務における対応ガイドラインをまとめています
その後、プロジェクトは社外、つまり社会へ向けたものへと発展します。デザイナーの役割はどのように拡大していきましたか?
林:
ハンドブックをきっかけに、プロジェクトのレギュラーメンバーとして参加するようになったんです。「東京レインボープライド」への出展にはじめて協力したのは2022年。グッズはステッカーだけだったと聞いています。けれど、パーソルキャリアをはじめグループの複数社が「PRIDE 指標」(※1)のゴールドに認定され、取り組みへの気運が一気に高まることに。2023年からはブースを拡大することになって、そこでVI(※2)の制作を依頼されたんです。
※1 LGBTQ+に関する取り組み指標
※2 ビジュアル・アイデンティティ:企業やブランドのコンセプトを目に見える形にし、メッセージを伝えるデザイン要素
抽象的な概念をデザインで「形」に
いよいよ表看板を作ることになったわけですね。パーソルグループのDEI推進にかける想いを表す大事なロゴです。要求は厳しかったのでは?
林:
それが、ほとんどゼロから任せてもらえたんです。まず、目的は1つ。DEI推進に関わった全員が「一人ひとり違いがあるのは特別なことではない」「誰もが自分らしくありのままでいてよい」と、あらためて思えること。その上で、デザインそのものへの具体的な要望は2つ。パーソルグループのブランドコンセプトに沿っていること、言葉を入れるなら「はたらいて、笑おう。」(英語版は“Work and Smile” ※)を用いることだけでした。
※当時は”Work, and Smile”
つまり、抽象的な概念からイメージを起こすことになったと。デザイナーにとってはうれしいような、困るような依頼ですね。
林:
ええ。こんなときこそ、日々広告デザイナーとして頭をひねっているみんなの腕の見せ所だなと。広告は制作前にコンセプトが言語化されていることが多いですが、ときに抽象的なこともあります。ですから、概念から本質を掴み、非言語的な表現としてアウトプットする作業には慣れています。制作統括部のデザイナー全員を巻き込んで、コンペを実施しました。

制作統括部はリモートワークが基本ですが、折に触れてオフィスで集まることも。ハイブリッドなワークスタイルはメリハリがついて良いそう
案を出したデザイナーにお聞きしたいです。はじめのオリエンを受けてどう思われましたか?
須田:
確かに依頼はフワッとしていました。けれど、却って思考がシンプルになったんです。アイディアの鍵は「レインボー」と「はたらいて、笑おう。」。他社の事例を見ると、どうやら幾何学模様をつかったわかりやすいものが多い。グッズにするのだからみんなが普段から着たり、使ったりしたくなるデザインがいいだろう。そうして逡巡しているときに「あ!」と――
レインボーが笑顔に?
不意にイメージが降りてきたんですか?
須田:
「レインボーって半円だ」と。これ、逆さにしたら笑った口になるんじゃないかって。
林:
最終的に採用されたのがその須田さんの案だったんです。はじめに見たときから意図が明確だと感じました。レインボーを逆さにして、笑顔! シンプルだけど、ハッとするほど芯が通っている。会社が表現したいビジョンと目線が合っているなって。
須田:
実は、レインボーを逆さにすることに当初は躊躇いがあったんです。ネガティブな表現ととらえられないだろうかと。しかし、ひっくり返したのではなく、回転させたんだ。ロールすることで幸せが拡がっていくんだ。そう逆説的に解釈すれば、レインボー、笑顔、拡がる幸せ――と、意味が幾重にも重なっていくことにも気づきました。
直接的にメッセージを伝える広告とは違った、アーティスティックなアプローチですね。依頼主の反応は?
須田:
大きな軌道修正はなく、ほぼストレートにこの案が通りました。ひとつ変更したのは、カラーリングです。はじめは赤やオレンジ、それぞれ一色ずつでバリエーションを持たせていたのですが、依頼主からの意見ですべてレインボー・カラーに統一することに。結果的に、メッセージが明確になったと思います。クライアントとの意見交換でアウトプットが磨かれていくのは、広告の仕事と同じですね。

左がカラーごとにバリエーションを持たせた初稿案。右がカラーを統一した最終版。LGBTQ+のPRIDEのシンボルとしてのレインボー・カラーは7色ではなく、国内外でこの6色が一般的に使われている
6色のグラデーションに込めた思い
2024年にかけて、年を追うごとにグッズの種類は増えました。なかにはVIとは違うデザインのものもありますね。
林:
パーソルのロゴにレインボー・カラーのグラデーションをあしらったものです。こちらは播本さんが制作してくれました。

普通のグラデーションとは一味違うように見えます。発想の起点を聞かせていただけますか?
播本:
6色からなるレインボー・カラーは色々な意味を持っていると思ったんです。単に多様であるということだけでなく、それぞれが混ざり合ってより美しくなる。思い出したのは水彩絵の具でした。子供のころ、パレットの上で色を混ぜるだけで楽しくて、延々と絵筆を回していた、あの感覚です。混ぜることで、明るくなったり、きれいになったり、新しいものが次々と生まれていく。
須田:
イラストも得意な播本さんならではの感性ですよね。
新井:
グッズを並べるとわかりますが、ホワイトをベースにしたVIとのコントラストで、それぞれがぐっと際立ちます。一人ではなく、みんなで制作したからこその成果ですね。

スマイルをモチーフにしたものと、グラデーションをベースにしたもの。2種類のデザインがグッズをより華やかでわくわくするものに
会場で感じた熱気と、発信者としての責任
では、会場でデザインを披露したときのことを聞かせてください。グッズをブースに並べ、配ってみて、いかがでしたか?
林:
シンプルに、ものを渡して、反応が返ってくる! 普段の業務はWebが中心ということもあり画面越しでしかユーザーの反応を得られないので、いつもとは違う感動がありました。
播本:
私は会場には行けなかったのですが、自分がデザインしたウェットティッシュが好評だったと聞いてうれしかったです。
広告は特定のターゲットに伝えますが、今回のようなソーシャルアクションは社会全体にメッセージを送るものだと思います。やはり普段の仕事とは別物でしょうか。
新井:
いいえ、デザインがコミュニケーションの起点になるという点では、大きな違いはないと思います。会場では、大人から子供までさまざまな年齢、ジェンダー、バックグラウンドの方たちと出会いました。声をかけて、グッズを手渡しして、誘導して。自分たちがつくったデザインが媒介になって会話が生まれることがうれしかったです。例えば年配の方が、かつてセクシュアルマイノリティとして生きづらさを感じてきた過去を、お話ししてくださったり。

「東京レインボープライド」会場ではデザイナー自身がスタッフとしてブースに立った。デザインが手触りのあるモノとなり、来場者へのギフトとなり、人と人をつないだ
林:
新井くん、お店の人みたいに上手だった!
(一同笑)
いわば、広告制作の仕事を発展させたようなものだった、というわけですね。
林:
私は普段の業務とは違う角度で、事業者としての責任を感じました。LGBTQ+に関するテーマは、まだまだナイーブなところもあります。世の中の風向きがどう変わるかわかりません。けれど、社会に生きる私たち全員がこのテーマの当事者。人材に関わる企業として、正しく発信しつづけなければいけないんだと思いを新たにしました。
デザインは、メッセージだ
最後は今一度、広告デザイナーの視点でお話しください。今回のプロジェクトにおいて、普段の仕事が生きたこと、あるいは今後普段の仕事に生かせることは何でしょうか?
播本:
率直に、今回の仕事は制限がたくさんあると感じました。センシティブな課題、抽象的だけれど強いメッセージ、そして受け手の反応。神経質になる要素は普段より多い上に、それをビジュアルのみでアウトプットしなければならない。難題でした。
でも、それって広告でも求められているはずだと気づいたんです。ビジュアルでいかに“メッセージ”を伝えていくか。仕事でも心がけてきたつもりだけれど、まだまだ甘かったんだなって。

制作したクリエイティブを振り返りながら意見交換。ロジカルな分析、設計があってこそ、発想の飛躍が生まれるそう
須田:
最短距離で、即座に伝える。より多くの人に、よりわかりやすく伝える。これは広告であっても、マスに向けたクリエイティブであっても変わらないんだということが、最大の発見でした。カメラに例えれば、焦点が小さいか、大きいかという違いだけなんです。そういう意味では、広告制作の経験は大いに生きたと思います。
林:
私も「伝える」ということの大切さを再認識しました。会場でグッズを手渡すと、「なんの会社?」って聞かれたんです。ただビジュアルを気に入ってもらうだけではいけなくて、自分たちは何者なのか? どんな事業をやっているのか? このグッズを通して何を発信したいのか? 一所懸命に語っている自分がいました。デザインは、作り手がメッセージを内在化してはじめて意味を持つんですね。
やはり、今回のプロジェクトは、みなさんだからこそ成し遂げられたんですね。ダイナミックな経験をお話しいただき、ありがとうございました。
-

林 園子 さん
採用ソリューション事業部 制作部 アートディレクター/デザイナー
美術大学を卒業しWEB 制作会社でキャリアをスタート。その後、お菓子メーカーのインハウスデザイナーに転身し、ブランドサイトやキャンペーンサイト、新商品のプロモーションサイトの制作に携わる。2016年パーソルキャリア入社。dodaの求人広告デザインを多数手がけ、2020年からはクライアント企業の採用プロモーションを支援するコンテンツビルドチームに所属し、WEBサイトやパンフレットをはじめとする各種採用コミュニケーションツールの企画制作を担当。一方でパーソルキャリアのプロダクト開発プロジェクトも兼務し、クライアントワークと自社サービスを共に手掛け、領域を横断したデザイン活動をおこなっている。
-
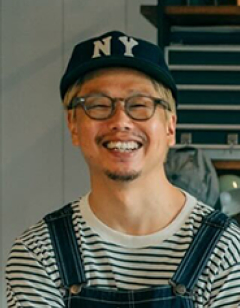
須田 俊一郎 さん
採用ソリューション事業部 制作部 デザイナー
広告の営業職としてキャリアをスタートし、2012年にパーソルグループに入社。IT関連の職務に従事したのち、自ら異動を希望して現在のポジションに。デザイン未経験から実績を積み、doda求人広告の制作では幾度も社内のアワード受賞。
-

播本 未来 さん
採用ソリューション事業部 制作部 デザイナー
インハウスデザイナーとして経験を積んだのち、2018年にフォトグラファーとしてパーソルキャリアに入社。広告取材における多様なロケ撮影、人物撮影で表現の幅を広げ、再度デザイナーへ転向。さらにはイラストレーターとしても社内外で活躍するマルチクリエイター。
-

新井 光治 さん
採用ソリューション事業部 制作部 デザイナー
20代半ばに一度デザイナーの仕事から離れるも、「やっぱりデザインを職業にしたい!」とキャリアをリスタート。制作会社を経て2023年にパーソルキャリアに入社。現在はクライアントへの企画提案もこなす。
※ 所属・肩書および仕事内容は、取材当時のものです。
執筆:林 太一
























(NUTIONで一緒にデザインしませんか?)
未知の領域へ越境し、成長し続けていきたい人。「はたらく」へのデザインを通じ、より社会へ貢献できる仕事がしたい人。NUTIONは、そんな価値観を共有できる仲間を探しています。








東京レインボープライド、お疲れさまでした。まずは、みなさんが「RainbowPERSOL」(※)の活動に参画したきっかけを教えてください。